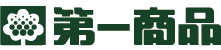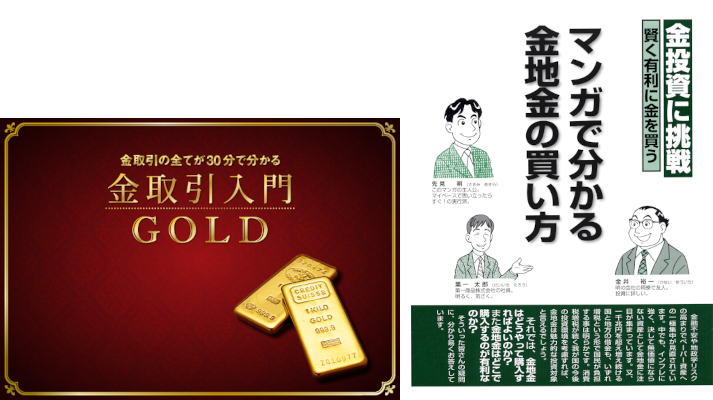金市況・ニュース
- 12日のNY金は下落、対主要国通貨でのドル高を受け5月13日 08:4012日のNY金は下落。指標限月6月物の清算値(終値)は前日比29.1ドル高の1824.6ドルとなった。
米連邦準備制度理事会(FRB)がインフレ高進に対して積極的に金融政策の引き締めや利上げを実施するとの見方から、多国籍通貨との金利差を意識したドル買いが進行。ドル建てNY金は割高感からの売りに押されて下落した。米FRBによる金利上昇が世界の経済成長を鈍化させるとの懸念から安全資産としてドルが選好された。
イエレン米財務長官は12日、下院金融サービス委員会の公聴会で、米FRBはリセッション(景気後退)を引き起こすことなくインフレを引き下げることができるとの考えを示しているが、米国以外の国への影響については言及していない。また、中国の景気悪化が欧州経済に波及するとの見方からもユーロ売りドル買いが進行した。 - 12日の金ETFは減少、現物保有量は1060.82トン5月13日 08:27ニューヨーク証券取引所に上場されている世界最大規模の金ETF「SPDRゴールド・シェア」現物保有量は、12日時点で前日比5.80トン減の1,060.82トンとなった。
また、「SPDRゴールド・シェア」の現物保有量は5月12日現在、昨年12月末と比べ85.16トン増加している。 - 11日のNY金は上伸、ドル安やインフレ圧力の継続見通しなど背景に5月12日 08:5811日のNY金は上伸。指標限月6月物の清算値(終値)は前日比12.7ドル高の1853.7ドルとなった。
米労働省が11日に発表した4月の米消費者物価指数(CPI)は前年同月比8.3%上昇となり、市場予想(同8.1%上昇)を上回った。ただ、前月(同8.5%上昇)よりも伸びが鈍化していたため市場の反応が割れ、インフレ圧力の強さを背景とした米連邦準備理事会(FRB)の利上げペースの加速観測から、発表直後は対主要国通貨でのドル高が進行し、ドル建てNY金は一時1830.6ドルまで下落した。
しかし、売り一巡後は、欧州中央銀行(ECB)のラガルド総裁の早期利上げに前向きとも取れる発言を受けドルが対ユーロで軟化したことや、米CPIの伸びは鈍化したが高インフレは当面続く可能性が高いとの見方などを手掛かりに金は買い戻された。
ラガルドECB総裁は11日の講演で、ECBは第3四半期初めに資産購入プログラムを終了する可能性が高く、初回の利上げは純資産購入の終了から「しばらく」後となるが、その期間は「数週間」後になるかもしれないとの見解を示した。また、ロシア産天然ガスの欧州への供給が減少したことや中国のエネルギー需要減少観測の後退を受けて原油価格が上昇したことが、エネルギー価格上昇によるインフレ圧力の継続見通しを強めている。 - 11日の金ETFは減少、現物保有量は1066.62トン5月12日 08:27ニューヨーク証券取引所に上場されている世界最大規模の金ETF「SPDRゴールド・シェア」現物保有量は、11日時点で前日比2.03トン減の1066.62トンとなった。
また、「SPDRゴールド・シェア」の現物保有量は5月11日現在、昨年12月末と比べ90.96トン増加している。 - 10日のNY金は下落、米FRBの利上げ観測や中国の景気後退懸念など受け5月11日 08:4110日のNY金は下落。指標限月6月物の清算値(終値)は前日比17.6ドル安の1841.0ドルとなった。
米連邦準備制度理事会(FRB)がインフレ抑制のために今後も利上げを積極的に行うとの見方が、金利を生まない資産である金の弱材料。4月の米消費者物価指数(CPI)の発表を11日(日本時間11日21時30分)に控えることや、対主要国通貨でのドル高進行も整理売り圧力を強めた。
また、世界最大の金消費国である中国の景気後退懸念も相場の圧迫材料。中国は新型コロナウイルス感染拡大防止のために実施しているロックダウン(都市封鎖)により、中国税関総署が9日発表した4月の貿易統計によると、輸出は前年同月比3.9%増となり、前月の14.7%増から大幅に鈍化した。中国は伝統的に金が選好され、個人の購入が金の需要を支えるため、同国経済の後退は金の需要の減少見通しを強めることになる。 - 10日の金ETFは減少、現物保有量は1068.65トン5月11日 08:20ニューヨーク証券取引所に上場されている世界最大規模の金ETF「SPDRゴールド・シェア」現物保有量は、10日時点で前日比7.25トン減の1068.65トンとなった。
また、「SPDRゴールド・シェア」の現物保有量は5月10日現在、昨年12月末と比べ92.99トン増加している。 - 9日のNY金は下落、ドル高や米金利上昇を受け5月10日 09:279日のNY金は下落。指標限月6月物の清算値(終値)は前日比24.2ドル安の1858.6ドルとなった。
米連邦準備理事会(FRB)が積極的にインフレを抑制して行くとの見方から米国債利回りが上昇し、対主要国通貨でのドル高が進行。ドル建てNY金は、割高感からの売りや、金利の上昇により保有することの機会費用が上昇することを嫌気した売りなどが入り下落した。また、11日(日本時間11日21時30分)に発表予定の4月の米消費者物価指数(CPI)の市場予想が前年同月比8.1%上昇と、前回の8.5%の伸びから鈍化するとみられていることも積極的な買いが手控えられる要因となった。 - 9日の金ETFは減少、現物保有量は1075.90トン5月10日 08:27ニューヨーク証券取引所に上場されている世界最大規模の金ETF「SPDRゴールド・シェア」現物保有量は、9日時点で前日比6.10トン減の1075.90トンとなった。
また、「SPDRゴールド・シェア」の現物保有量は5月9日現在、昨年12月末と比べ100.24トン増加している。 - 6日のNY金は上伸、対ユーロでのドル安を受け5月9日 08:556日のNY金は上伸。指標限月6月物の清算値(終値)は前日比7.1ドル高の1882.8ドルとなった。
欧州中央銀行(ECB)当局者らのタカ派発言を受け、ECBが7月の理事会までに利上げを実施するとの見方が強まったことから、ユーロ買いドル売りが進行。ドル建てNY金は割安感からの買いが入り上伸した。ただ、米労働省は6日、4月の米雇用統計は非農業部門雇用者数が前月比42万8000人増、4月の米失業率は3.6%と前月から横ばいと発表。景気動向を示すとされる非農業部門雇用者数が市場予想(39万1000人増)を上回り、米連邦準備制度理事会(FRB)が金融引き締め姿勢をさらに強めるとの警戒感が一部で再燃し、米長期金利の指標となる10年債利回りが上昇したことが、金利を生まない資産である金の上値を押さえた。
また、今回4月の米雇用統計では、時間当たり平均賃金は前月比0.3%上昇と、伸びは前月の0.5%から鈍化。賃金の上昇ペースが鈍化したことで、米国のインフレがピークを迎えたのではないかとの見方を強めている。このため、市場の関心は5月11日発表予定の4月の米消費者物価指数(CPI)へと向けられているとの指摘も聞かれた。 - 6日の金ETFは減少、現物保有量は1082.00トン5月9日 08:20ニューヨーク証券取引所に上場されている世界最大規模の金ETF「SPDRゴールド・シェア」現物保有量は、6日時点で前日比2.98トン減の1082.00トンとなった。
また、「SPDRゴールド・シェア」の現物保有量は5月6日現在、昨年12月末と比べ106.34トン増加している。 - 5日のNY金は上伸、国内連休中に大幅下落5月6日 09:105日のNY金は上伸。指標限月6月物の清算値(終値)は前日比6.9ドル高の1875.7ドルとなった。ただし、国内連休中のNY金は下落。4月29日終値1915.1ドルと比べて39.4ドル下落している。
4日に公表された米連邦公開市場委員会(FOMC)声明は、政策金利となるフェデラル・ファンド(FF)レートの誘導目標を50ベーシスポイント(bp)引き上げ、6月に保有資産の縮小に着手することを決定する、ほぼ市場予想通りの内容となった。しかし、パウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長は同日の記者会見での質疑応答で更に大幅な利上げについて「積極的に」検討しないと発言したことを受け、4日のNYダウ平均は900ドル超の上げ幅を記録する一方、NY金は下落。その後、5日にはNYダウ平均は急落し、NY金は買い戻されて上伸する、荒い値動きとなった。
パウエル米FRB議長の発言を巡り市場の見方が分かれたことで米株式市場は乱高下したが、金融市場では中長期的な米政策金利は年末までに2.7%まで引き上げられるとの見通しを織り込んでいることや、米FRBの積極的な利上げによる米経済回復の後退懸念などが台頭し、NY金は安全資産としての買いに支えられた。しかし、対主要国通貨でのドル高が進行し、主要6通貨で構成されるドル指数は2002年12月以来、約20年ぶりの高値をつけたことに頭を押さえられ、NY金の戻りは限られた。 - 5日の金ETFは減少、現物保有量は1084.98トン5月6日 08:34ニューヨーク証券取引所に上場されている世界最大規模の金ETF「SPDRゴールド・シェア」現物保有量は、5日時点で前日比4.06トン減の1084.98トンとなった。
また、「SPDRゴールド・シェア」の現物保有量は5月5日現在、昨年12月末と比べ109.32トン増加している。 - 3日の金ETFは減少、現物保有量は1089.04トン5月6日 08:33ニューヨーク証券取引所に上場されている世界最大規模の金ETF「SPDRゴールド・シェア」現物保有量は、3日時点で前日比3.19トン減の1089.04トンとなった。
また、「SPDRゴールド・シェア」の現物保有量は5月3日現在、昨年12月末と比べ113.38トン増加している。 - 2日の金ETFは減少、現物保有量は1092.23トン5月6日 08:33ニューヨーク証券取引所に上場されている世界最大規模の金ETF「SPDRゴールド・シェア」現物保有量は、2日時点で前日比2.32トン減の1092.23トンとなった。
また、「SPDRゴールド・シェア」の現物保有量は5月2日現在、昨年12月末と比べ116.57トン増加している。 - 29日のNY金は上伸、米ドル高の一服を眺め5月2日 08:50NY金は上伸。指標限月6月物の清算値(終値)は前日比20.40ドル高の1911.70ドルとなった。
欧州連合(EU)統計局が29日発表した4月のユーロ圏消費者物価指数(HICP)速報値は前年比7.5%上昇となり過去最大の伸び率を更新。これを受け、欧州中央銀行(ECB)が年末までに実施する利上げ幅への市場の予想が上方修正されると共に、月末要因から利益確定の売りなども入り、ユーロ買いドル売りが進行。20年ぶりの高値圏に浮上していた主要6通貨に対するドル指数が下落すると共に、ドル建てNY金は割安感からの買いにも支えられて上伸した。
祝日により国内市場が休場だった前日の28日には下落したが、市場の焦点が5月3日、4日両日開催の米連邦公開市場委員会(FOMC)に向けられていることもあり、調整主導に買い戻される動きとなった。 - 29日の金ETFは減少、現物保有量は1094.55トン5月2日 08:27ニューヨーク証券取引所に上場されている世界最大規模の金ETF「SPDRゴールド・シェア」現物保有量は、4月29日時点で前日比1.16トン減の1094.55トンとなった。
また、「SPDRゴールド・シェア」の現物保有量は4月29日現在、昨年12月末と比べ118.89トン増加している。 - 27日のNY金は軟調、対ユーロでのドル高が圧迫4月28日 09:0127日のNY金は軟調。指標限月6月物の清算値(終値)は前日比15.40ドル安の1888.70ドルとなった。
ロシア国営の天然ガス大手ガスプロムは27日、ロシア通貨ルーブルの支払いに応じなかったとしてブルガリアとポーランドへの天然ガスの供給を停止。欧州地域のエネルギー需給のひっ迫がユーロ圏経済を下押しするとの警戒感が強まったことで、ユーロ売り・ドル買いが進行。主要6通貨で構成されるドル指数も上昇し、ドル建てNY金は割高感からの売りが入り下落した。また、来週の米連邦公開市場委員会(FOMC)で利上げが行われると予想されていることも、金利を生まない資産である金の上値を押さえた。 - 27日の金ETFは減少、現物保有量は1095.72トン4月28日 08:52ニューヨーク証券取引所に上場されている世界最大規模の金ETF「SPDRゴールド・シェア」現物保有量は、4月27日時点で前日比5.51トン減の1095.72トンとなった。
また、「SPDRゴールド・シェア」の現物保有量は4月27日現在、昨年12月末と比べ120.06トン増加している。 - 26日のNY金は上伸、米長期金利の下落などを手掛かりに4月27日 08:3026日のNY金は上伸。指標限月6月物の清算値(終値)は前日比8.10ドル高の1904.10ドルとなった。
中国の新型コロナウイルス対策としてのロックダウン(都市封鎖)により、同国を中心に世界経済が減速するとの懸念から米長期金利が下落したことが、金利を生まない資産である金にとっては支援材料。また、テクニカル主導の買戻しも入り、1トロイオンス=1900ドル台を回復して取引を終えた。
ただ、来週の米公開市場委員会(FOMC)で米連邦準備制度理事会(FRB)がバランスシートの縮小と追加利上げを実施すると見られていることや、対主要国通貨でのドル高進行が相場の上値を圧迫した。 - 25日のNY金は下落、中国の需要減少観測やドル高を受け4月26日 09:0525日のNY金は下落。指標限月6月物の清算値(終値)は前日比38.30ドル安の1896.00ドルとなった。
中国での新型コロナウイルスの感染対策が強化されたことで、主要なエネルギー輸入・消費国である中国の景気後退への懸念が高まると共に、原油価格が下落。エネルギー価格高騰を背景としたインフレ高進への懸念が後退。中国での金購入の多くは個人投資家が担うため、感染対策が強化され市民の行動が制限される中では金購入の減少が見込まれることなども圧迫材料となり、金は下落した。
また、来週に控えた米連邦公開市場委員会(FOMC)で0.5%の大幅利上げに踏み切るとの見方から、対主要国通貨でのドル高が継続。ドル建てNY金は割高感からの売りも入り、2か月ぶりの安値圏に値を沈めた。
※ 当社提供のs情報について
本サービスは、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的として提供するものではありません。投資方針や時期選択等の最終判断はご自身で判断されますようお願いいたします。なお、本サービスにより利用者の皆様に生じたいかなる損害についても、第一商品は一切の責任を負いかねますことをご了承願います。