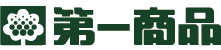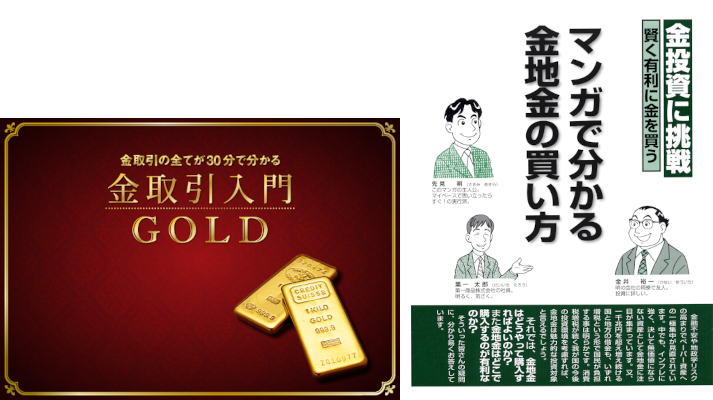金市況・ニュース
- 17日の金ETFは増加、現物保有量は1075.54トン6月20日 08:40ニューヨーク証券取引所に上場されている世界最大規模の金ETF「SPDRゴールド・シェア」現物保有量は、17日時点で前日比11.6トン増の1075.54トンとなった。
また、「SPDRゴールド・シェア」の現物保有量は14日現在、昨年12月末と比べ99.88トン増加している。 - 16日のNY金は上伸、世界的な景気後退懸念やドル安を受け6月17日 08:5016日のNY金は上伸。指標限月8月物の清算値(終値)は前日比30.3ドル高の1849.9ドルとなった。
スイス国立銀行(中央銀行)とイングランド銀行(英中央銀行)が利上げを決定したことで、各国主要中銀がインフレ抑制のために金融引き締めを実施することで、世界経済の減速や景気後退(リセッション)につながるとの懸念が台頭。また、スイス国立銀行の利上げは市場の想定外だったため、スイスフランが対ドルや対ユーロで急伸。ドル建てNY金はドル安をみた割安感からの買いや、インフレヘッジとしての買いが入り、清算値確定後の時間外取引では1850ドル台を回復している。 - 15日のNY金は上伸、米FRBの大幅利上げを受けた米景気の減速懸念などが台頭6月16日 09:0315日のNY金は上伸。指標限月8月物の清算値(終値)は前日比6.1ドル高の1819.6ドルとなった。
米連邦公開市場委員会(FOMC)声明において、米連邦準備制度理事会(FRB)は、通常の3倍となる0.75%の大幅利上げを決定。米FOMC参加者による最新の金利・経済見通しではフェデラル・ファンド(FF)金利見通しが2022年末で3.4%と、前回3月末時点の見通し(22年末1.9%)から大幅に引き上げられた。
米FOMC声明発表直後は対主要国通貨でドル高に振れたが、その後のパウエル米FRB議長の会見で利上げに対しての慎重姿勢が示されたことで、引けにかけてドル安が進行。材料出尽くし感や米景気の減速懸念が強まる中で、ドル建てNY金は割安感からの買いや安全資産としての買いなどが入り、清算値確定後の時間外取引で値を伸ばし、9時時点では前日比15.1ドル高の1834.70ドルで推移している。 - 14日のNY金は下落、米FRBの大幅利上げ観測を背景に6月15日 08:4314日のNY金は下落。指標限月8月物の清算値(終値)は前日比18.3ドル安の1813.5ドルとなった。
米連邦準備制度理事会(FRB)が14日、15日両日開催の米連邦公開市場委員会(FOMC)で大幅利上げを実施するとの見方から、対主要国通貨でのドル高が進行。ドル建てNY金は割高感からの売りが入り下落。米労働省が14日発表した5月の米卸売物価指数(PPI)は前月比0.8%上昇し、4月の0.4%上昇から伸びが加速。インフレ圧力が強まれば、米FRBは9月以降の積極利上げを迫られる可能性があるとの見方も、金利を生まない資産である金にとっては弱材料となった。 市場では先週10日に発表された5月の米消費者物価指数(CPI)が1981年12月以来、40年5カ月ぶりの大幅な上昇率を記録したことから、米FRBは従来予想よりも早いペースでの利上げを実施するとの観測が台頭。米債券市場では、米FRBが0.75%の利上げを実施する可能性を織り込む動きが広がっている。 - 14日の金ETFは減少、現物保有量は1063.94トン6月15日 08:33ニューヨーク証券取引所に上場されている世界最大規模の金ETF「SPDRゴールド・シェア」現物保有量は、14日時点で前日比4.93トン減の1063.94トンとなった。
また、「SPDRゴールド・シェア」の現物保有量は14日現在、昨年12月末と比べ88.28トン増加している。 - 13日のNY金は下落、対主要国通貨でのドル高を受け6月14日 08:4913日のNY金は下落。指標限月8月物の清算値(終値)は前日比43.7ドル安の1831.8ドルとなった。
先週10日に発表された5月の米消費者物価指数(CPI)が市場予想を上回る高い伸びとなり、米国のインフレがピークを迎えたとの市場の思惑が後退すると共に、米連邦準備制度理事会(FRB)の積極利上げで、米経済はリセッション(景気後退)に陥るとの懸念が浮上。投資家のリスク選好姿勢が後退し、資産を現金化する動きが強まる中で、米株価は下落し、対主要国通貨でのドル高が進行。ドル建てNY金は割高感からの売りが入り下落した。 - 10日のNY金は上伸、米FRBの積極利上げへの懸念や米株安を受け6月13日 08:4510日のNY金は上伸。指標限月8月物の清算値(終値)は前日比22.7ドル高の1875.5ドルとなった。
10日に米労働省が発表した5月の米消費者物価指数(CPI)は前年度比8.6%上昇し、市場予想(8.3%上昇)を上回ると共に、1981年12月以来の高い伸びを示したことで、米連邦準備制度理事会(FRB)が積極的に利上げを実施するとの見方が浮上する一方、金利を生まない資産である金は下落した。ただ、売り一巡後は、積極的な金融引き締めが景気を冷やすとの懸念や、インフレ高進懸念が再燃する中、投資家のリスク選好姿勢が後退したことで米株価が急落。インフレヘッジとしての買いや安全資産としての買いが入り金は急反発する荒い値動きとなった。 - 10日の金ETFは増加、現物保有量は1068.87トン6月13日 08:20ニューヨーク証券取引所に上場されている世界最大規模の金ETF「SPDRゴールド・シェア」現物保有量は、10日時点で前日比3.48トン増の1068.87トンとなった。
また、「SPDRゴールド・シェア」の現物保有量は10日現在、昨年12月末と比べ93.21トン増加している。 - 9日のNY金は軟調、ECB理事会や米金利上昇などを受け6月10日 08:599日のNY金は軟調。指標限月8月物の清算値(終値)は前日比3.7ドル安の1852.8ドルとなった。
欧州中央銀行(ECB)は9日の理事会で、量的緩和策の資産購入プログラム(APP)を7月1日に終了し、同月の次回会合で約11年ぶりに利上げに踏み切る方針を表明。また、インフレが沈静化しなければ、9月に大幅な利上げを行う意向も示した。これを受け、米長期金利の指標となる米10年債利回りが上昇したことが、金利を生まない資産である金にとっては弱材料。また、対ユーロでのドル高が進行し、ドル建てNY金は割高感からの売りも入り下落した。
また、金融政策の正常化が欧州景気に悪影響を与えるとの懸念や、中国上海の一部地域が新型コロナウイルス感染症拡大防止のためロックダウン(都市封鎖)が再度行われるとの報を受け、原油需要が減少するとの見方からNY原油が軟化したことも、インフレヘッジとしての金需要を後退させた。 - 8日のNY金は上伸、ECB理事会など控えた調整主導の動き6月9日 09:128日のNY金は上伸。指標限月8月物の清算値(終値)は前日比4.4ドル高の1856.5ドルとなった。
世界的なインフレに対し、各国中央銀行が政策金利の引き上げを実施するとの見方が金利を生まない資産である金の上値を押さえる一方、積極的な政策金利の引き上げが景気へ悪影響を与える可能性があるとの懸念から安全資産としての買いが入ったほか、原油の上伸を眺めたインフレヘッジとしての買いが値を支えた。ただ、10日に米消費者物価指数(CPI)の発表を控えることや、各国中央銀行の動きを睨み、全体的には調整主導の動きに留まっている。
豪州中央銀行は7日の定例理事会で政策金利を市場予想を上回る0.50%引き上げ。イエレン米財務長官は7日の上院財政委員会で、米国は「許容できない」水準のインフレに対処していると発言。また、5月のユーロ圏のインフレ率が過去最高の8.1%に達しているため、欧州中央銀行(ECB)は9日の理事会で0.25%の利上げを実施した後、9月までの利上げに対する地均しを行うと予想されている。 - 8日の金ETFは増加、現物保有量は1065.39トン6月9日 08:25ニューヨーク証券取引所に上場されている世界最大規模の金ETF「SPDRゴールド・シェア」現物保有量は、8日時点で前日比2.32トン増の1065.39トンとなった。
また、「SPDRゴールド・シェア」の現物保有量は8日現在、昨年12月末と比べ89.73トン増加している。 - 7日のNY金は上伸、米国債利回りの下落や対ユーロでのドル安を受け6月8日 08:587日のNY金は上伸。指標限月8月物の清算値(終値)は前日比8.4ドル高の1852.1ドルとなった。
米国のインフレが最悪期を脱したとの見方から、米長期金利の指標となる米10年債利回りが低下。対ユーロでのドル安が進行し、ドル建てNY金は割安感からの買いが入り上伸した。10日に発表を控える5月の米消費者物価指数(CPI)がインフレの高止まりを示す結果になるとの見方や、各国中央銀行が高インフレを抑えるために積極的な金融引き締めを進め、経済成長が圧迫されることへの懸念も根強く、6月9日の欧州中央銀行(ECB)理事会や来週の米連邦公開市場委員会(FOMC)へと市場の注目が向けられている。 - 6日のNY金は下落、米債券利回りの上昇を受け6月7日 08:586日のNY金は下落。指標限月8月物の清算値(終値)は前日比6.5ドル安の1843.7ドルとなった。
10日発表の米消費者物価指数(CPI)がインフレの高止まりを示すと予想される中、米長期金利の指標となる米10年債利回りが上昇。金利を生まない資産である金にとっては弱材料となった。また、対主要国通貨でのドル高が進行し、ドル建てNY金は割高感からの売りが入り下落した。6月と7月の米連邦公開市場委員会(FOMC)では、米連邦準備制度理事会(FRB)が0.50%の利上げを実施すると予想される中、今週発表予定の米CPIへ市場の注目が向けられている。高いインフレ率が記録されれば、今年下半期も積極的な利上げが実施されるとの予想が強まると考えられている。 - 6日の金ETFは減少、現物保有量は1063.07トン6月7日 08:36ニューヨーク証券取引所に上場されている世界最大規模の金ETF「SPDRゴールド・シェア」現物保有量は、6日時点で前日比2.97トン減の1063.07トンとなった。
また、「SPDRゴールド・シェア」の現物保有量は6日現在、昨年12月末と比べ87.41トン増加している。 - 3日のNY金は下落、堅調な米雇用統計を受け6月6日 08:503日のNY金は下落。指標限月8月物の清算値(終値)は前日比21.2ドル安の1850.2ドルとなった。
3日に米労働省が発表した5月の米雇用統計によると、非農業部門雇用者数は前月比39万人増と、市場予想の32万5000人増を上回り、米連邦準備理事会(FRB)が良好な雇用情勢を背景に積極的な利上げを進める可能性があるとの見方から、対主要国通貨でのドル高が進行。ドル建てNY金は割高感からの売りが入り下落した。 - 2日のNY金は上伸、原油高やドル安などを受け6月3日 09:122日のNY金は上伸。指標限月8月物の清算値(終値)は前日比22.7ドル高の1871.4ドルとなった。
石油輸出国機構(OPEC)加盟国とロシアなど非加盟国で構成する「OPECプラス」が2日、増産ペース拡大で合意したが、ロシアの石油生産量の落ち込みを穴埋めするには足りないとの見方から、原油が上伸。米民間雇用サービス会社ADPが2日発表した5月の全米雇用報告は、非農業部門の民間就業者数が前月比12万8000人増と、市場予想の30万人を下回ったことで米国の景気後退懸念が強まったことや、中国上海市が新型コロナウイルス対策のロックダウン(都市封鎖)を2か月ぶりに解除されるとの報を受け、投資家のリスク選好姿勢が高まると共に、安全資産として買われていた米ドルが下落。ドル建てNY金は割安感からの買いやインフレヘッジとしての買いなども入り上伸した。 - 2日の金ETFは減少、現物保有量は1066.04トン6月3日 08:42ニューヨーク証券取引所に上場されている世界最大規模の金ETF「SPDRゴールド・シェア」現物保有量は、2日時点で前日比1.16トン減の1066.04トンとなった。
また、「SPDRゴールド・シェア」の現物保有量は2日現在、昨年12月末と比べ90.38トン増加している。 - 1日のNY金は堅調、世界的なインフレ懸念を背景に6月2日 09:051日のNY金は堅調。指標限月8月物の清算値(終値)は前日比0.3ドル高の1848.7ドルとなった。
世界的なインフレが予想以上に進行しているとの見方から、インフレヘッジとしての買いに支えられ、金は上伸した。
イエレン米財務長官は31日、過去のインフレ見通しについて自身が間違っていたとの認識を示すと共に、現在の米政権にとってインフレ抑制が最優先事項であるとの考えを発言。また、フランス国立統計経済研究所(INSEE)が31日発表した5月の欧州連合(EU)基準の消費者物価指数(CPI)速報値は、前年同月比5.8%上昇し、市場予想(5.6%上昇)を上回ると共に、4月の5.4%上昇から加速。ドイツの5月のインフレ率が過去最大(EU基準で前年同月比8.7%上昇)となったこともあり、欧州地域のインフレは予想以上に加速しているとの見方が強まっている。 - 1日の金ETFは減少、現物保有量は1067.20トン6月2日 08:30ニューヨーク証券取引所に上場されている世界最大規模の金ETF「SPDRゴールド・シェア」現物保有量は、1日時点で前日比1.16トン減の1067.20トンとなった。
また、「SPDRゴールド・シェア」の現物保有量は1日現在、昨年12月末と比べ91.54トン増加している。 - 31日のNY金は下落、米利回り上昇や対主要国通貨でのドル高を受け6月1日 08:4231日のNY金は下落。指標限月8月物の清算値(終値)は前日比8.9ドル安の1848.4ドルとなった。
欧州連合(EU)統計局が31日発表した5月のユーロ圏消費者物価指数(HICP)速報値は前年同月比8.1%上昇し、再び過去最高を更新。更に同日発表された3月の米ケース・シラー住宅価格指数が前年比21.2%上昇となり、伸びが過去最高を記録したことなどを受け、世界的なインフレ高進への懸念が再度強まると共に、米長期金利の指標となる米10年債利回りが上昇し、金利を生まない資産である金は下落。また、対主要国通貨でのドル高が進行し、ドル建てNY金は割高感からの売りも入り下落した。
※ 当社提供のs情報について
本サービスは、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的として提供するものではありません。投資方針や時期選択等の最終判断はご自身で判断されますようお願いいたします。なお、本サービスにより利用者の皆様に生じたいかなる損害についても、第一商品は一切の責任を負いかねますことをご了承願います。